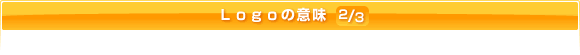
・個人が、自身の属する7つの社会とどのように
付き合うか?を決める
・個人は「能動」 − 7つの社会に対して「できること」
・会社視点からステークホルダーに対し
IR、CS、ESを提供する
・個人は「受動」 − 会社に対して「できること」
 今までの「価値観」とは? 今までの「価値観」とは?
今までは、「会社至上主義」ということで、「会社が中心」のものの捉え方でした。
まずは、会社を中心に顧客や生活者に対してCS(Customer Satisfaction:顧客満足)を高めることに重きを置いて経営してきたトレンドがありました。
続いて、会社のステークホルダーは株主であるという主張が強まった頃に、IR(Investor Relations:投資家向け広報)という形で株主に報いるというトレンドができました。
もちろん会社に属している個人も会社からはES(Employee Satisfaction)という形で、「社員の幸せが会社の幸せに繋がる」ということで多くの配慮が設けられました。
とはいえ、個人は基本的には「受動的」立場にあって、会社に対してできることとは何か?という視点であったと思います。
 次にくる新しい「価値観」とは? 次にくる新しい「価値観」とは?
では、次にくる新しい「価値観」とはどのようなものでしょうか?
それは「個人」が中心にくるものの考え方だと思います。個人と繋がりをもつ側面は凡そ7つに整理されると考えました。それは、 (1)先人・両親 (2)夫婦・パートナー (3)子供 (4)友人 (5)地域 (6)趣味 (7)会社です。今まで (7)会社と自分という社会しかないと思わされていたのですが、他の社会との関わりが無視できない状況になってきています。たとえば、 (7)会社一辺倒だと (2)家庭崩壊、そうなると仕事が手につかなくなる人も多いですよね。これは、会社と自分、夫妻と自分という2つの社会があって、優先順位をどうおきながら生きていくかを決めなければなりません。
会社と自分というのは収入を得る手段として存在し続けるとしても、「どの社会とどのように付き合っていくのか?」を自分で決め、かつ他の人の価値観も受容しながら共生していく、という社会に変わっていくのではないかな、と感じています(個人中心と言っても、勝手気まま・自分だけ主義ではないことにご留意ください)。とすれば、個人は「能動的」立場に変わるわけです。
近年「下流社会」や「格差社会」という言葉をよく耳にするのですが、これらをよくよく読み込むと、結局は「自分で価値基準を決めて、それに対して正直に生きていけるかどうかが差を生んでいく」というのがメッセージだと思います。安易な格差の話ではないですよね。
|

